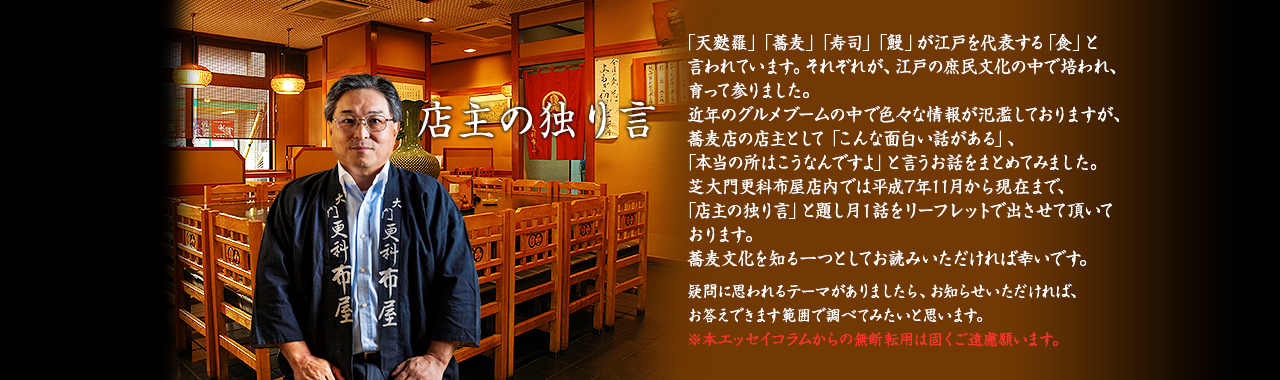2025年4月 第191話 地回り醤油
そば汁の材料「醤油」は日本人の食卓に欠かせない調味料ですが「濃口」「淡口」「溜り」と、製法によって独特の味わいと風味の違いを作り出します。その違いや味を劇的に変えて行った原因が江戸前の料理だと言われています。醤油の起源は定かでは無いのですが、飛鳥時代に中国から朝鮮半島を経て伝わってきた「醤(ひしお)」がその原型であろうと言われています。
「醤」には魚類を発酵させた魚醤、野菜や海草を使った漬物の様な草醤、穀物や豆を発酵させた穀醤等があり醤油はこの内の穀醤の一つだと思われます。醤から最初に生まれた「溜り醤油」は醸造期間が3年程度でしたが、人口の急増で需要が拡大した関東ではそんな長時間では供給が間に合わず、如何に短時間で醤油を作るかが大きな命題であり、数ヶ月から1年で製品となる「濃口醤油」が寛永期の終り(17世紀中頃)に作り出されました。当時の江戸では地場産の醤油を「地廻り醤油」と呼んでいました。
画期的な発明ではあった濃口醤油ですが、江戸での醤油のシェアは関西からの「下り醤油」が圧倒的でした。
関西でも関東同様、醸造期間の短い「淡口醤油」が17世紀後半に考案され,溜りとは違った味の醤油となりましたが、それでもやはり人気は上物とされた「下り醤油」でした。まだこの時代はなかなか陽の目を見れない「地廻り醤油」なのです。
醤油が一般的に普及する江戸後期までは、刺身には日本酒と梅干と鰹節を煮詰めた「煎り酒」が使われていましたし、我々のお蕎麦は1升の味噌に3升5合の水を加えて3升まで煮詰めて漉した「垂れ味噌」と言う調味料が使われていました。そうした中、文化・文政期(18世紀後半から19世紀初頭)に江戸で大ブレイクを始めた蕎麦・寿司・鰻・天麩羅と言う江戸4大料理が醤油に大変動をもたらすのです。
江戸料理にとっては醤油との相性が味の根底になります。淡口の下り醤油ではさすがに江戸料理を支える力にはなりません。
そこで香りとコクに富んだ「地廻りの濃口醤油」が一気に台頭する事となりました。
18世紀の間、約80%のシェアを誇った下り醤油は百年後には何と2%を切るまでになったと言う統計が残っています。
この大逆転の最大の理由は、旧来の原料の大豆に小麦を同量加えて香りを高くすると言った品質向上が「甘好き」で知られた江戸っ子にマッチした事であるとされています。甘さ=美味さとした江戸料理と地廻り醤油の出合いが江戸っ子の味覚を生み出したと言っても過言ではないと思われる事実です。